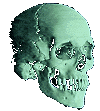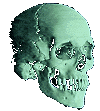ホーム/創作/日記
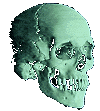
『最後のミステリ』

『判決、被告人を死刑に処す』 .
俺の中の言葉が、俺を制御しているようだった。俺の手の中の光る化け物
が、目の前の男の腹に食らい付いていた。香織の胸に突き刺さっていた、あ
の忌まわしいナイフ。しかし、そんな得体の知れない衝動とは裏腹に、俺の
心は冷めていた。 .
「、、、だから、それが出来たのは、たった一人しかありえない。『悪魔』
の正体は山田、あんただ!」 .
「フハハハハハ、、、」 .
山田はうずくまりながら笑っていた。腹から赤黒い液体を吐き出し続けな
がら。 .
「これで完成だ、完成なんだ」 .
「どういう意味だ?」 .
「わからないのか、これこそが『最後のミステリ』なのさ。その本を手に取
ってみろ、お前がこの事件の始まるときから、読み続けている本を。お前の
手記にも何度も出ていたはずだ。しかし、その内容については一言も書かれ
ていない。『いくら読んでも、中身は頭の中に入って来なかった』、そんな
描写すらある。どうだ、今なら思い出せるか?どんな内容だった?」 .
頭がくらくらしていた。本の中身が思い出せないなんてことはよくある話
じゃないか。そんなに真剣に読んでなかっただけだ。しかし、確かに俺は、
事件の間ずっとこの本を読み続けていたような気もする。いや、考えるな、
考えちゃいけない。考えれば、何かに取り込まれてしまいそうだ。 .
「では、聞こう、その本の題名は何だ?」 .
それすら思い出せなかった。俺は本を手に取った。何度も何度も読み返し
たような、手垢の付いたその本を。表紙に書かれていた文字は、『最後のミ
ステリ』だった。 .
「10年前、俺が書いた本だ。お前は取り憑かれたように、その本に夢中に
なっていたのさ。だから、簡単だった。ちょっとした暗示で、お前はそれを
現実だと思い込むようになった。虚構の中に生きる身になったんだ。そして
俺が与えた暗示は、もう一つある」 .
「言うな!」俺は叫んでいた。 .
「俺が言わなくても、もうわかってるだろうに。そうさ、俺はお前に暗示を
与えたのさ。『裁け!』と」 .
ハハハハハ、と奴の高笑いが響く。 .
「『神の声を聞く名探偵』だと。嗤わせるな。それならば、俺こそが、悪魔
であり、神であるというわけだ。お前は俺の声を、俺の暗示が導いた言葉を
聞いていただけなんだからな。そうさ、俺が書いたミステリは、作者が犯人
である小説だった。そして、探偵による作者殺しに終わる。ちょうど今、お
前が俺を刺したように」 .
くくくくく、と今度は含み笑いに変わった。 .
「しかし、お前が手記を書くとは、とんだ拾い物だったよ。それでこそ、俺
のミステリは完成したんだからな。俺の本と、お前の手記、二つが合わさっ
て、完全なミステリになり得たんだ。俺自身が『最後のミステリ』であると
言ってもいいはずだ。俺は犯人であり、被害者であり、探偵を導くものとし
て探偵の上位にいるものだ。そしてまた、俺はこのミステリの作者であり、
同時にまた、読者でもある。ハハハ、完璧じゃないか」 .
「そんなことはどうでもいい!何故だ、何故俺を苦しめる?どうして俺に、
こんな地獄の苦しみを与えるんだ!」 .
「どうでもよくはないのさ。苦しみだと。馬鹿を言うな。俺は悪魔であり、
同時に神だ。お前に苦しみを与えてなどいない。祝福を与えてやったのさ。
ここがどこかぐらいはお前にもわかっているだろう。新宿のど真ん中のビル
の中さ。それにしては、一切の物音がないとは思わんか。俺にはある種の能
力がある。強烈な暗示の力もその一つだがな。だから、わかるんだ。もはや
この世界に人間はお前と俺しか残っちゃいないんだ」 .
「ば、ばかな。そんなことがあるわけないじゃないか。核戦争でも起こった
というのか」 .
「核だと、そんな大仰なもんじゃない。俺も未だに信じられないんだが、き
っかけはたった1本のビデオテープだったらしい。それこそもう、どうでも
いい話だがな、くっ、、、」 .
奴は顔を歪めた。時折痙攣が走ったように身体が震える。最期の時が近づ
いて来ているようだった。 .
「俺が死ぬことでミステリは終焉する。お前一人ではもはや、殺し殺される
ことは出来ないんだからな。俺がこの手で『最後のミステリ』を産み出した
んだ。そして、お前が『最後のミステリ読者』なんだ。読み手としてこんな
名誉なことはあるまい、、、これが、、お前に与、、、える祝福、、、だ」
ひときわ激しい痙攣が、奴を襲い、やがて沈黙した。奴の言葉を信じるな
らば、全世界が俺に残されたのだ。そんな途方もない財産など、俺には全く
不要だというのに。 .
そうさ、奴の言葉を信じる必要性などどこにある。ミステリに取り憑かれ
た男の誇大妄想、幻想に過ぎないのさ。確かに奴はミステリ作家としては、
才能に恵まれていた。この、おそらくは防音設備の整ったビルの中で、そん
なねじれた天才の妄想に、ちょっとした影響を受けただけさ。こんな歪んだ
時空から逃れることなど、造作もないことだ。単に扉を開けてみればいい。
きっと、そこから日常が中に流れ込んでくるに違いないだろう。 .
だから、ここでペンを置くことにしよう。 .
‥‥‥扉の向こうに、答がある‥‥‥
(終)