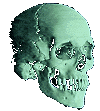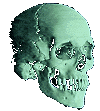ホーム/創作/日記
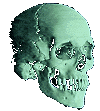
「匣の中の失楽」評
[ QMC(九大ミステリ愛好会)部誌「断崖」
第三号('84.1.31発行)所収の書評の再録 ]

 「虚無への供物」と「匣の中の失楽」の
「虚無への供物」と「匣の中の失楽」の
ネタバレがありますので、未読の方はご注意下さい!

「黒死館」「虚無」「ドグラ」に続く作品があったのかと、僕
はこの本を手にした。この本の狙い目はこの特殊な構成にある。
一章毎に真実と虚構とが入れ替わる。それ自体を含む大きな架空
の中で。 .
三章の冒頭でやっとそれに気付いたとき、僕は正直言って愕然
とした。こんな構成があったのか。作中作を用いて、偶数章、奇
数章のどちらを取るかは読者の裁断に任せる。様々な部分でお手
本にしている「虚無への供物」の壮大なアンチミステリーたる結
末に対する挑戦としては、充分価値あろう。 .
しかし、これは中途での感想である。何故なら竹本健治は最後
に至って、それを放棄してしまったからだ。そうとしか思えな.
い。どうして六章が存在していないんだ!五章の収束に比べて、
四章の中途半端なお粗末さはどういうわけだ。六章で偶数章の収
束を決定付け、それら全てをつなぎ合わせる線としての序章と終
章があるはずだ。終章、特にナイルズの独白は二重の意味を持つ
ものでなくてはならない。そうしてこそ初めて「虚無」に挑戦し
得る一種のアンチミステリー(ふさわしくなければ、壮大なリド
ルストーリーとしてもよい)としての存在価値が生まれるのであ
る。 .
僕の読み方が足りずに何らかの意義を見落としているのだろう
か?そうでないとすれば、存在しない六章がこの小説の最大の謎
である。 .
竹本健治という作者を無視し、実際にナイルズを作者として考
えるなら、この謎を解くヒントはある。つまり、さかさまの趣向
を完成させるためには、一方の探偵役は一方の犯人であり、一方
の犯人は一方の探偵役でなくてはならないのである。 .
僕の仮説を進めてみよう。終章のうち二重の意味を持ち得ない
ほとんどの部分が五章の完結部分に過ぎない。そして大事なのは
最後の根戸の告発は、本当はナイルズによって行われたという事
だ。六章の内容は四章のラストが実を結ぶのだ。誰(もしくは.
誰々)が探偵役になるかは五章により自明である。終章のうち、
唯一残っている最後の光景の一部、特に最後の二行の持つ意味は
こう考えてこそすっきりするのである。終章(本来は五章)での
真沼の登場は、ナイルズによる追悼でしかない。「−僕はどこに
いるの。−どこにもいないわ。」という詩が暗示するとおりであ
る。 .
そういう行為をどうして自由になし得たか。つまり偶数章こそ
現実であり、奇数章はナイルズの小説での架空であったからだ。
これで、謎の核心に迫ってきたものと思う。では、何故六章がな
いのか。一つには、最初から存在していないと考えてみることも
できる。犯人と看破されたナイルズの死によって。だが、一応存
在するものと考えるのが正解だろう。 .
ここで初めて、竹本健治なる人物の登場となる。ナイルズ(も
しくはメンバーの一人)から、この小説を受け取った彼は、もう
一つのでっかい”さかさまの趣向”を思いついたのである。つま
り、現実と虚構とをそっくり入れ替えてしまうというからくりで
ある。そのために彼は五章の後半以降を書き直したのである。.
(四章のラストの曳間による暗示は本来六章のものだったかもし
れない)一方では見事な二重構成を見せながら、突然片方のみに
寄り掛かってしまったという謎はこれで解ける。 .
そして何故こうしなければならなかったのか。明白である。言
葉による小説の中身での趣向では越えることの出来ないものがあ
る。小説という存在性そのものへの大トリック。それこそが唯一
の方法だと考えたのだ。つまり、「虚無への供物」において、小
説の中から読者へ向かって指をさした趣向へ対抗するために。.
まだまだ幾つもの問題点もあるし、言い足りないことも多々あ
る。一つの仮説として提出するにとどめおきたい。 .